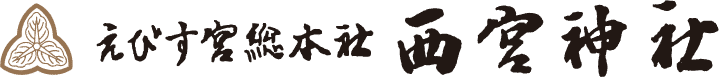ひゃくだゆうじんじゃ
- 御祭神百太夫神
- 例祭日1月5日
- 御神徳芸能の神、子供の守り神

『伊呂波字類抄』にも社名がみえることからも平安末期にはすでに祀られていました。
人形操りや散楽などの芸能に従事する傀儡子(百太夫)を祖神として祀るお社であり、元は境外の散所村(現 産所町)の傀儡子達の集落でお祀りしていたものを天保10年(1839)に境内に遷座しました。

百太夫について、えびす信仰の広がりと人形操り
伝説では百太夫は人形操りの技術に大変優れており、えびす大神の神慮を慰め祀るとともに多くの弟子を養育したと伝えられています。
えびす信仰が今日のように全国に広まったのは、この散所村に住んでいた人形遣いがえびすさまの御神徳を人形を操りえびす舞をしながら広めていったのが一つの要因と考えられています。
この人形遣い達は、江戸時代になると西宮を離れ淡路島に移ってしまい、現在は国の重要無形民俗文化財に指定されている淡路島の人形浄瑠璃や大阪の文楽となったと言われています。
また人形操りなどの芸能の神として以外にも疱瘡(天然痘)に霊験があると信仰されています。江戸時代に疱瘡が流行した際には8代将軍吉宗公もその病に伏したため百太夫のお札を祀ったと伝えられています。庶民信仰では子供の病気予防の為に御神体のお顔のおしろいを子どもの額につけて病気にかからぬまじないをする習わしがありました。